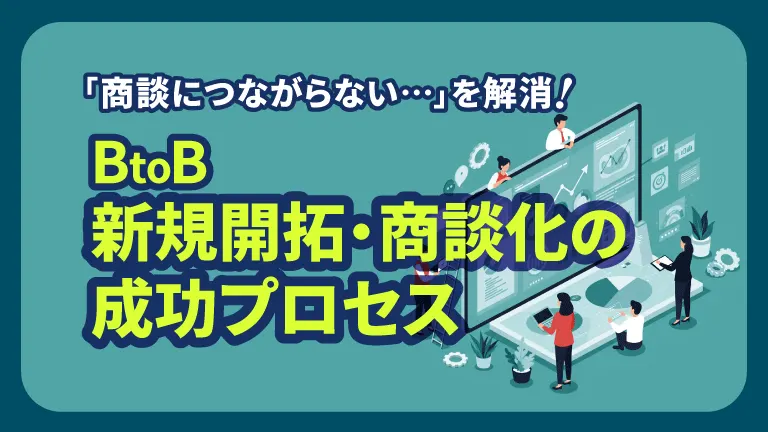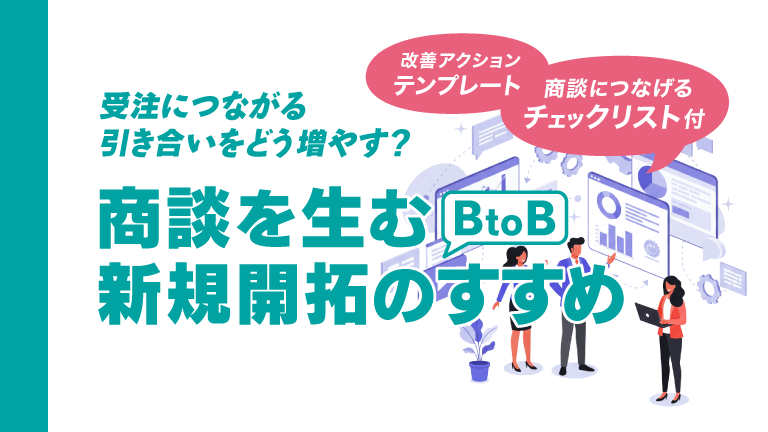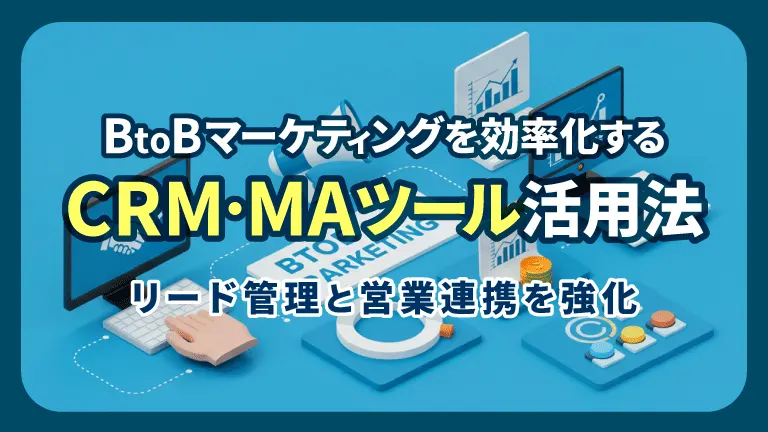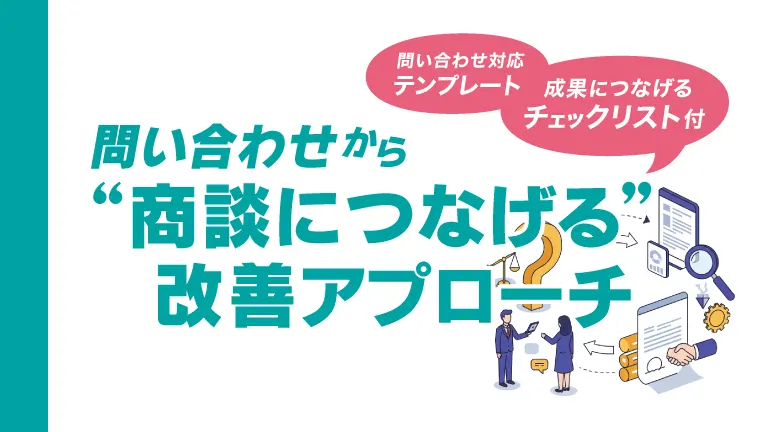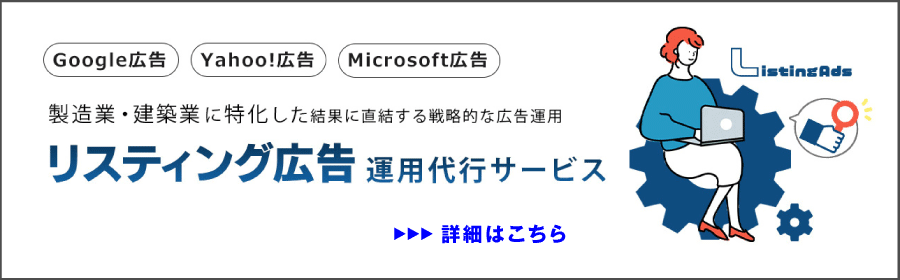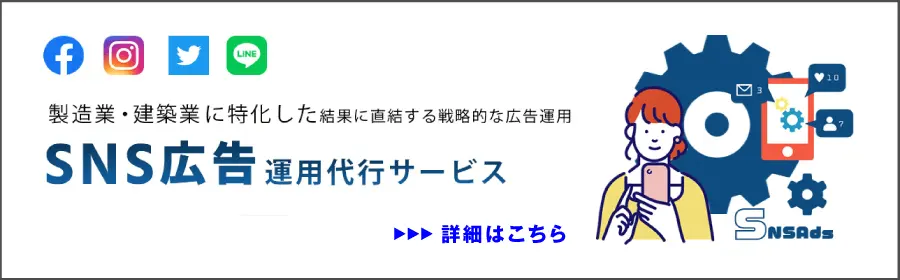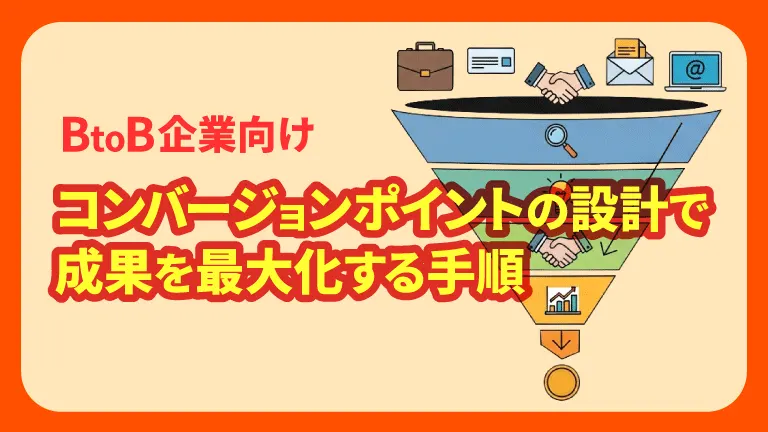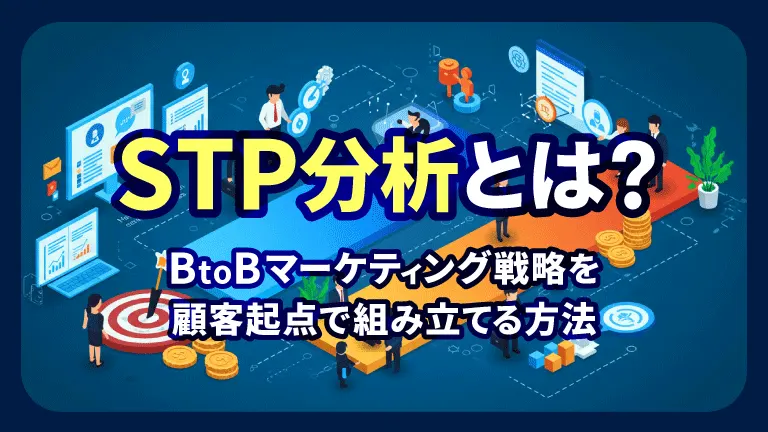「新規開拓に力を入れているのに、なかなか商談に結びつかない」
「問い合わせは増えてきたのに、そこから先に進まない」
そんな悩みを抱えるBtoB企業は少なくありません。
本記事では、新規開拓から商談化までを一貫して成功させるためのプロセスをわかりやすく解説します。マーケティングと営業の橋渡しに悩む担当者は、ぜひ参考にしてください。
商談を生む新規開拓のアプローチ
新規開拓の取り組みを続けているのに、なかなか商談につながらない──。
その原因は「努力不足」ではなく、戦略や施策の“方向性のずれ”にあることが少なくありません。市場環境や購買行動が変化する中で、従来の営業スタイルだけに依存していると、潜在顧客との接点を十分に築けないこともあります。
なぜ今、新規開拓が難しくなっているのか?
BtoB市場の成熟により、製品やサービスの品質が均質化する中で、「良いモノをつくれば売れる」時代は終わりました。製品のスペックや価格だけでは差別化が難しく、価格競争に巻き込まれやすくなっています。
特に製造業では、「技術力で勝負しているはずなのに、受注につながらない」といった課題も散見されます。製品自体の価値をどう伝えるか、市場の中でどのようなポジションを確立するか(ポジショニング戦略)が、これまで以上に問われています。
さらに、顧客の情報収集行動は大きく変化しています。営業担当者に会う前に、WebサイトやSNSなどで情報を得ることが当たり前になり、「会って話す前の段階」で勝負が決まるケースが増えています。
BtoB企業における購買プロセスの特徴
BtoBの購買プロセスは、次のような特徴を持っています。
- 複数の関与者による合議制
- 段階的で戦略的な意思決定プロセス
- 検討期間が長期化しやすい
BtoBにおける購買プロセスは長く複雑であり、実際には「比較検討フェーズ」に至る前に、現場担当者による「情報収集フェーズ」が存在します。ここでの接点を逃すと、貴社が候補にすら入らない可能性があります。
〈情報収集フェーズの特徴〉
- 課題の明確化前:解決策や製品名よりも「課題の理解」「一般的なトレンド」に関心
- 現場担当者中心:将来の意思決定者に情報を持ち上げる立場
- ニーズは潜在的:まだ「比較検討」ほど具体的ではない
〈情報収集フェーズの重要性〉
- 早期に接点を持つことで「第一想起」に入りやすい
- 担当者が上司に提案する際の「参考情報源」として利用される
- 比較検討フェーズに移行した際に「候補リスト」に残る
商品力や技術力があっても、知られていない企業や製品は、そもそも検討リストに入りません。情報収集フェーズで顧客と接点を持てるかどうかが、その後の比較検討フェーズで選ばれるかどうかを左右します。「まだ検討していない層」と思って後回しにするのではなく、早期の信頼関係構築が商談獲得の土台となります。
商談機会を逃す3つの課題
ここでは、商談機会を取りこぼしてしまう代表的な3つの課題を整理します。自社の取り組みと照らし合わせながら、どこに改善余地があるかを見直すヒントにしてください。
ターゲット設定のずれ
自社の強みや提供価値に対して、狙うべき顧客層が適切に定まっていないケースです。購買意思を持たない層にリーチしても、商談につながる確率は低くなります。市場や顧客ニーズを再定義し、「どんな課題を持つ企業に刺さるか」を明確にすることが重要です。
開拓チャネルの偏り
営業訪問や展示会など、従来型の接点だけに頼っていると、情報収集をオンラインで行う顧客にリーチできません。オンライン広告、SEO、SNSなど、複数チャネルを組み合わせて認知・興味喚起の機会を広げることが必要です。
リード獲得後の接点不足
名刺交換や資料請求などでリードを獲得しても、その後のフォローが不十分だと、検討リストから外れてしまいます。メールマーケティングやセミナー案内などで継続的に接点を持ち、検討タイミングに合わせて再アプローチできる仕組みが求められます。
| 課題 | 説明 | 改善の方向性 |
| ターゲット設定のずれ | 想定顧客像が曖昧で、的外れなアプローチになっている | 顧客の課題や検討フェーズを明確化し、セグメントごとに戦略を設計 |
| 開拓チャネルの偏り | オフライン中心・特定媒体依存など、接点が限定的 | オンライン施策(SEO、リスティング広告、SNSなど)と組み合わせて接点を拡大 |
| リード獲得後の接点不足 | 問い合わせ後のフォローやナーチャリングが不十分 | コンテンツ提供やメール施策で関係を維持・深化させる |
これらの課題を放置すると、せっかくの見込み顧客を逃してしまう“チャンスロス”につながります。「どこで商談機会を取りこぼしているのか」を可視化することが、最初の改善ステップです。
単に「リードを獲得する」だけでは不十分です。どのフェーズの“誰に”、どんな情報を、どのタイミングで届けるか──。この設計こそが、商談機会を生むための鍵となります。
対策:オンライン×顧客視点のアプローチが必須
現代のBtoB営業では、「まず会って話す」スタイルだけでは顧客の検討タイミングとズレてしまうリスクがあります。今の顧客は、自分のペースで比較・検討を進めたいと考えています。したがって、顧客が情報収集を行うタイミングで、自社を検討候補に入れてもらうことが重要です。
〈具体的な施策例〉
- 情報収集フェーズ(検討初期)
→「課題理解」や「業界トレンド」をテーマにしたコンテンツを発信
〈例〉課題解説記事、調査レポート、事例紹介、ウェビナー - 比較検討フェーズ
→ 導入事例や機能比較など、意思決定を後押しする情報を提供
〈例〉製品比較表、導入事例詳細 - 導入検討フェーズ
→ ROI(費用対効果)や実績など、安心感を与える要素を強化
〈例〉ROIシミュレーション、導入プロセス解説
これらを通して、リードを獲得した後も継続的に接点を持ち、関係を育てていく(リードナーチャリング)ことが、商談化の確率を高めます。
★詳しく知りたい方へ 関連記事 受注につながる引き合いをどう増やす?商談を生む BtoB新規開拓のすすめ[metaslider id="15593"]※ホワイトペーパーはお申込み完了後、DLページのリンクを送信します。商談機会を最大[…] |
問い合わせはあるのに、商談につながらない…
せっかく問い合わせを獲得しても、商談に発展しない──。
この「あと一歩届かない」状態には、営業・マーケティング双方のプロセスに共通する課題が潜んでいます。例えば、対応のタイミングが遅れたり、顧客の関心度に合わせた情報提供ができていなかったりと、わずかな行き違いが商談機会を失う要因となります。
商談化を阻む3つの要因
以下では、商談化を妨げる主な要因を3つの視点で整理しました。自社の営業プロセスに照らし合わせながら、改善のヒントを見つけてください。
問い合わせ後の対応スピードの遅れ
顧客が問い合わせをした直後は興味や関心が高い状態です。このタイミングでの対応が遅れると、商談化の機会を逃してしまいます。
顧客ステータスに応じた情報提供の不足
BtoBでは、顧客の関心度や購買意欲に応じて提供する情報を変えることが重要です。マーケティング用語では、関心度の高い見込み客を「SQL(Sales Qualified Lead)=営業がアプローチすべきリード」、まだ情報収集段階の顧客を「MQL(Marketing Qualified Lead)=マーケティングが育成すべきリード」と呼びます。これに応じた情報提供が不足すると、商談につながりにくくなります。
営業とマーケティングの連携不足
顧客情報や問い合わせ状況を営業とマーケティングで共有できていない場合、接触のタイミングや内容がズレてしまいます。リード(見込み顧客)の情報を整理・共有するために、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援ツール)を活用して情報を一元管理することで、担当者間の認識をそろえ、効率的な商談化が可能になります。
| 要因 | 内容 | 改善の方向性 |
| 対応スピードの遅れ | 問い合わせからの初動対応が遅いと、他社に流れてしまう | 初動の自動返信・即時フォロー体制を整備 |
| 顧客ステータスに応じた情報提供の不足 | リードの温度感を見極めず、同一対応をしてしまう | MQL・SQLなどの定義を設け、段階に応じたアプローチを実施 |
| 営業とマーケティングの連携不足 | データが共有されず、重複対応や機会損失が発生 | CRM・SFAで一元管理し、KPIを共有化する |
これら3つの要因を把握し、それぞれに対応する施策を講じることが、問い合わせを確実に商談へとつなげるためのポイントです。
BtoBマーケティングを効率化するCRM・MAツール活用法については、こちらの記事をご覧ください。 関連記事 BtoBマーケティングにおいて、CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールは、効率的な顧客管理・ターゲティング・パーソナライズ施策の中核を担う存在で[…] |
対策:BtoBサイトと営業活動を“つなぐ”
リード獲得まではマーケティング部門、商談化以降は営業部門──。このように分断されてしまうと、情報が途切れ、せっかくの見込み顧客を逃してしまいます。重要なのは、「Webで得た情報」と「営業現場での接点」を一貫して管理する仕組みです。
例えば以下のような取り組みが効果的です。
- CRM/SFAツールによる顧客データの一元管理
- リードスコアリングで商談確度を可視化
- 定期的な営業・マーケティング会議で情報共有
このように、データと人の動きをつなぐことで、「問い合わせで終わらせず、商談へつなげる」仕組みが構築できます。
★詳しく知りたい方へ 関連記事 問い合わせから“商談につなげる”改善アプローチ[metaslider id="15378"]※ホワイトペーパーはお申込み完了後、DLページのリンクを送信します。問い合わせから確実に商談へ―改善アプローチを[…] |
まとめ:売る力ではなく、“伝える力”を磨く
BtoBの営業成果を高めるうえで見直すべきは、「売り込みの強さ」ではなく「伝え方の設計」です。
- 顧客の検討フェーズに合わせた情報提供
- マーケティングと営業の一貫した連携
- オンラインとオフラインをつなぐ仕組み化
この3点を軸に、自社の新規開拓・商談化プロセスを見直すことで、“がんばっているのに成果が出ない”という状況を脱し、受注につながる仕組みを築くことができます。
弊社ではWeb集客の分析や改善提案など、製造業・建築業に特化したデジタルマーケティングのプロがトータルサポートを行っております。いつでもご相談ください。