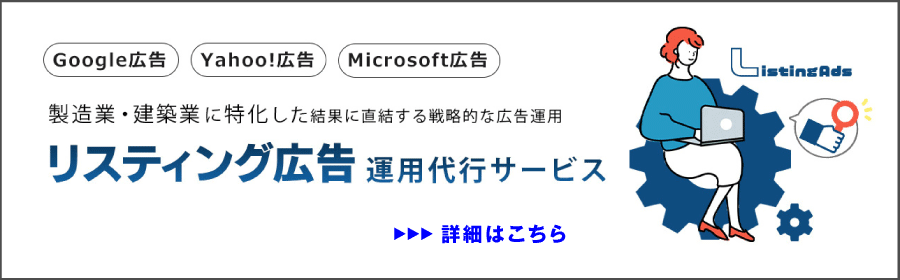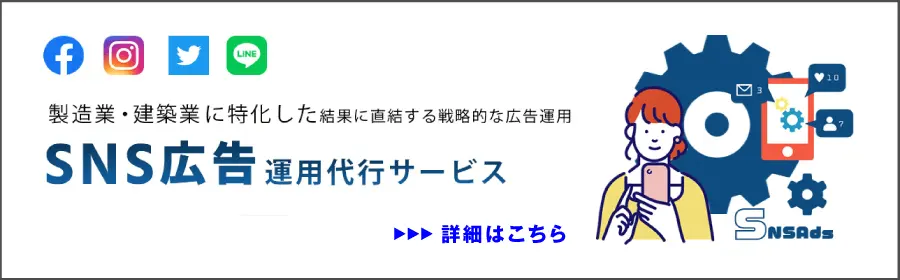リターゲティング(リマーケティング)は、一度自社サイトに訪れたことのあるユーザーに対して広告を再配信できる手法です。
近年、Cookie規制などの影響もありますが、顕在層ユーザーへのアプローチや広告効果の最適化を図るうえで、依然として重要な広告戦略のひとつです。
この記事では、リターゲティングの仕組み・広告の種類・メリット・活用のコツまでわかりやすく解説します。
リターゲティングとは?
リターゲティング(リマーケティング)とは、一度自社サイトに訪問したユーザーに再び広告を配信する仕組みです。
Google広告では「リマーケティング」Yahoo!広告では「サイトリターゲティング」と呼ばれます。※この記事では「リターゲティング」で表記を統一しています。
Cookieを活用した広告配信
リターゲティングでは、ユーザーが自社のWebサイトを訪れた際に、そのブラウザにCookie(識別情報)を付与します。このCookie情報をもとに広告プラットフォームがユーザーを特定し、後日、別のWebサイトやアプリを閲覧している際に広告を表示します。
なお、近年ではブラウザやOSによるサードパーティCookieの制限も進んでおり、GoogleもChromeでの段階的廃止を進めています。そのため、ファーストパーティデータやコンテキストターゲティングと併用したリターゲティング戦略がより重要になっています。
Webサイトを見ているとよく目にする「Cookie(クッキー)」って、聞いたことがあるけど具体的にはよくわからないという方も多いと思います。最近はCookieの使用について同意を求めるポップアップが表示されるケースも増えてきて、同意してよい[…]
リターゲティング広告の種類と分類
リターゲティング広告には、配信内容やターゲティング方法によってさまざまな種類があります。ここでは「広告の動的・静的な性質」および「ターゲティング方法」に分類して紹介します。
動的 vs 静的 リターゲティング
【静的リターゲティング(Static Retargeting)】
あらかじめ用意したクリエイティブを用いて、指定のユーザーリストに対して一律の広告を配信します。設定が比較的簡単で、ブランド訴求に向いています。
例えば、製造業向けの測定機器メーカーが「精度・導入実績・カタログ請求」などを訴求する一般的なバナー広告を、サイト訪問者全体に向けて配信するケースです。
検討期間が長くなる傾向のあるBtoBにおいて、繰り返しブランドや製品カテゴリーを想起させたい場合に有効です。
- 認知向上やブランドの刷り込みに向いている
- 製品ラインが少ない場合でも適用しやすい
- 初期導入が容易で運用のハードルが低い
【動的リターゲティング】
ユーザーが過去に閲覧したページ内容(製品ページや資料ページなど)に応じて、パーソナライズされた広告クリエイティブを自動生成し配信します。
例えば、産業用ロボットメーカーのサイトで「アーム型ロボットA」「協働ロボットB」など複数の製品ページを持っている場合、ユーザーが閲覧した製品に応じて、その製品に関連する導入事例や資料請求バナーを動的に生成して配信できます。
- 製品ラインナップが多い企業に有効
- 興味・検討度の高い見込み顧客に対し、個別の提案ができる
- 導入事例や比較コンテンツなど、検討ステージに応じた広告設計が可能
リターゲティングの主要な種類
【標準リターゲティング】
広告主のWebサイト訪問履歴をもとに、ディスプレイ広告ネットワーク上で広告を配信。
【検索広告向けリターゲティングリスト(RLSA)】
自社のWebサイトを訪問したことがあるユーザーに対して、検索広告の入札調整や広告内容のカスタマイズが可能。
【動画リマーケティング】
YouTubeなどで自社動画を視聴したユーザーに、後日ディスプレイ広告を表示。
【アプリリターゲティング】
広告主が所持するアプリ(AndroidやiOS)の行動履歴を基にユーザーリストを作成し、広告を配信。
【Googleアナリティクスベースのリマーケティング】
自社サイト上の行動データ(ページ閲覧数や滞在時間など)を基にユーザーリストを作成し、広告を配信。
【顧客リストに基づくリマーケティング】
広告主の持つ顧客の連絡先情報(メールアドレスや電話番号、住所など)をアップロードして、マッチしたユーザーに広告を配信。
リターゲティングのメリットと重要性
リターゲティング広告は、特定の行動を取ったユーザーに再接触できるため、広告効果の最大化に役立ちます。
リターケティングのメリット
コンバージョン率(CVR)の向上
購買や問い合わせの直前で離脱したユーザーに再アプローチできるため、コンバージョン率(CVR)の向上が期待できます。
例えば、セミナー参加ページを閲覧した購買担当者に対して、導入成功事例の広告を表示することで、行動を後押ししやすくなります。
広告費用対効果(ROAS)の最適化
興味・関心の高いユーザー層に絞って広告を配信するため、無駄なインプレッションやクリックが減り、限られた予算内でも高い広告効果が期待できます。
例えば、汎用的なキーワード広告よりも、再訪ユーザーに対するリターゲティング広告の方が、CPA(顧客獲得単価)を低く抑えられるケースがあります。
リターケティングの重要性
顕在層ユーザーの取りこぼし防止
検討段階にある見込み顧客との継続的な接点を維持することで、競合他社への流出を防ぎ、購買や問い合わせにつなげることができます。
ブランド認知・想起の強化
BtoB商材は高単価かつ長期契約が多く、信頼性やブランドイメージが意思決定に大きな影響を与えます。
繰り返し広告に接触することで、企業名や製品カテゴリの認知度を高め、指名検索や直接訪問といった具体的な行動へとつながります。
リターゲティング活用のコツ
リターゲティングの効果を最大限に引き出すには、「ユーザーの行動に応じたリスト分け」と「広告の出し分け」がポイントになります。
時間経過でリストを分ける
ユーザーがサイトを訪問してから時間が経つと購買意欲が下がる可能性があるため、適切なタイミングで適切なメッセージを届けることが重要です。
■訪問3日以内:強くアプローチ
| ねらい | 検討意欲が高いうちに、行動を促す |
| 広告の内容例 | 「今なら○○資料を無料でダウンロード」 「導入事例まとめ・今すぐチェック」 「○○業界の導入実績、一覧公開中」 |
| 具体的な施策 | ・バナー配信(カタログ請求やお問い合わせページへのリンク) ・特定製品に関心を示したユーザーには、その製品に特化した機能紹介や活用事例を動的広告で表示 ・価格やROI(投資利益率)に関する情報を明記し、購買意思決定を後押しする |
■訪問4〜7日:検討を促す内容
| ねらい | 関心を維持しながら、比較・検討フェーズへ導く |
| 広告の内容例 | 「競合製品との違いがわかる比較資料」 「○○導入で業務効率が30%向上」 「失敗しない製品選定チェックリスト」 |
| 具体的な施策 | ・比較表・チェックリスト・FAQなどを誘導先に設定したコンテンツ広告を配信 ・セミナーやウェビナーなど、「学び直し」や「社内稟議に使える」情報コンテンツへの誘導 ・CTAを「再検討のきっかけ」に変える (例:「迷っている方へ」「選ばれる理由を見る」) |
■訪問8〜30日:再興味を引く訴求
| ねらい | 記憶が薄れたユーザーに再度関心を呼び起こす |
| 広告の内容例 | 「導入企業のリアルな声を公開中」 「期間限定 ○○業界向け特別コンテンツ配布中」 |
| 具体的な施策 | ・顧客インタビュー動画やブログ記事など、読み物コンテンツへの誘導 ・業界ニュースや事例紹介で間接的に製品価値を再訴求 |
ページの深さ(サイト内行動)で分ける
ページ閲覧の深度=関心度と捉えて、以下のように分類することで、より効果的な配信が可能になります。
■トップページだけ閲覧:関心が浅い
| ねらい | 幅広い認知とライトな関心層への入り口作り |
| 広告の内容例 | 「○○業界の課題を解決するヒント」 「製品ラインナップを見る」 「無料で使える○○チェックリスト」 |
| 具体的な施策 | ・業界課題やユースケースを紹介するブログ記事へ誘導 ・ブランドや会社全体の訴求(導入実績など) ・興味を深めてもらうための動画コンテンツやホワイトペーパーを案内 |
■商品・サービスページ閲覧:興味あり
| ねらい | 検討フェーズに入りかけたユーザーの意思を後押し |
| 広告の内容例 | 「他社はこう使っている!○○活用事例」 「製品別資料をまとめて比較」 「○○製品の導入ステップ公開中」 |
| 具体的な施策 | ・該当製品に関する導入事例・成功事例を動的に表示 ・資料請求・見積もり依頼への再誘導広告 ・導入プロセスや技術支援体制の紹介 |
■お問い合わせ・資料請求ページ閲覧:購買意欲が高い
| ねらい | 最終意思決定を後押しし、行動へとつなげる |
| 広告の内容例 | 「導入前によくある質問まとめ」 「サポート体制・料金について詳しく」 「今なら初回相談無料受付中」 |
| 具体的な施策 | ・CTAを強化したリマインド広告(例:「まだご相談予約は完了していません」) ・オンライン相談会や営業担当への直接コンタクトを促す誘導 ・個別サポート・無料診断など、行動ハードルを下げる訴求 |
これらの戦略は、ユーザーの心理状態や検討ステージに合わせて「押しすぎず、引きすぎず」のバランスで広告を出し分けることがポイントです。
特にBtoBの場合は、検討が長期化しやすいため、焦らず継続的な接点設計が成果を左右します。。
まとめ
リターゲティングは、顕在層ユーザーを効率的に取り込むことができる非常に有効な広告施策です。
動的配信やリストのセグメント化を活用すれば、広告効果の最大化と費用対効果の改善が見込めます。
ただし、配信のしすぎによる「追い回し感」やブランドイメージ低下には注意が必要です。
ユーザーの行動や心理を尊重した設計で、効果的に活用していきましょう。
弊社ではWeb集客の分析や改善提案など、製造業・建築業に特化したデジタルマーケティングのプロがトータルサポートを行っております。いつでもご相談ください。